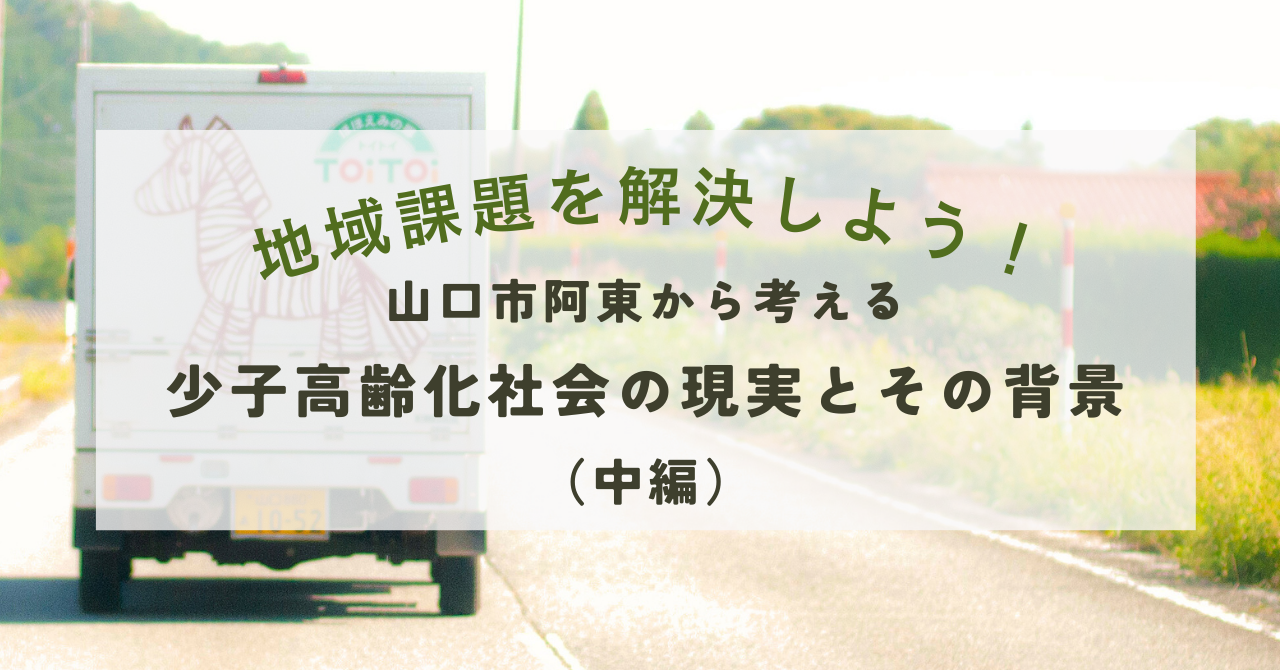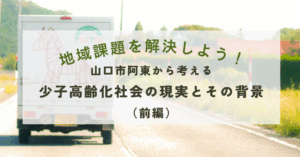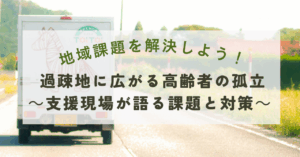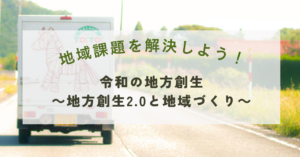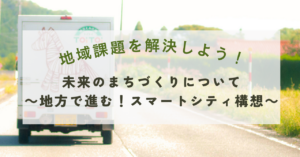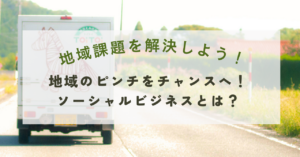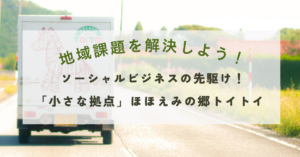深夜、泣き続ける赤ちゃんを抱え、夫婦だけで家事と育児に追われる光景――阿東の現実を知ったとき、私は少子高齢化社会の影響が身近な問題だと実感しました。
前編では、少子高齢化社会が日本全体に与える影響を概観し、特に阿東地域の現状に焦点を当てました。都会で暮らしていた頃は「人口減少」「高齢化」「少子高齢化社会」といった言葉は遠い問題に感じられましたが、実際に阿東に移住してみると、それが日常生活に深く影響していることを実感するようになった、という体験を紹介しました。
具体的には、以下の課題が取り上げました。
- 高齢化の進行と人口減少に伴う地域コミュニティの衰退
- 医療・介護の担い手不足
- 子育て環境の厳しさと若年層の減少
地域医療の担い手不足については、別記事(山口市阿東の地域医療の現実|高齢化社会で“病院に行かない暮らし”が当たり前に)で詳しく触れています。
山口市阿東の地域医療の現実|高齢化社会で“病院に行かない暮らし”が当たり前に
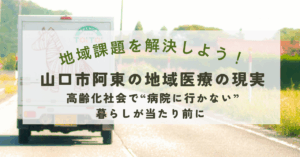
前編ではこうした課題の概要と地域への影響を整理しましたが、中編ではさらに踏み込み、阿東での具体的な現状や地域文化、子育ての実態、そして三世代同居の再評価など、現場の声を交えながら「少子高齢化社会が日常生活にどう影響しているか」を詳しく探っていきます。
日本の少子高齢化社会の現状と社会的影響
国連の「World Population Prospects 2022」(United Nations, World Population Prospects 2022)によれば、日本の人口は今後数十年で1億人を下回ると予測されています。2050年には高齢者(65歳以上)の割合が40%近くに達するとされ、世界的にも突出した高齢社会を迎えようとしています。2050年には高齢化率40%とされますが、阿東地域ではすでに近い水準に達しており、日本の未来を先取りしているといえますね。
さらに内閣府の将来推計(内閣府「高齢化の推移と将来推計」)でも同様の見通しが示されており、労働力人口の減少や社会保障制度の持続困難といった現実が目前に迫っています。少子高齢化は、もはや避けられない社会構造の大転換と言えるでしょう。
労働力の減少
若年層の減少に伴い、労働力人口が縮小。特に農業、中小企業、サービス業では深刻な人材不足が起こり、地域経済の衰退を加速させています。
社会保障制度の危機
高齢者の増加により、年金・医療・介護費は膨張。一方で税収を支える現役世代は減少し、制度の持続性に不安が広がっています。
地域の過疎化と限界集落化
都市への人口集中が進む一方で、地方は急速に過疎化。中山間地域では高齢化が一層進み、学校や病院の閉鎖など地域コミュニティの基盤が揺らいでいます。山口市阿東でも高校の閉校や病院の閉院が続き、「人がいない」という現実を目の当たりにしています。
少子高齢化社会での子育て、核家族ゆえのワンオペ育児
阿東で暮らしていると、子育て世代から「この地域での育児の大変さ」をよく耳にします。移住してきたママさんはこう話していました。
「頼れる親族が近くにいないし、共働きで子育ても家事もすべて夫婦だけ。夜泣きで眠れないまま翌日も仕事に行くなんてことが続くと、本当に精神的に追い込まれます。」
「終日ひとりで向き合う育児のストレスから、子どもに手をだしそうになったことも正直ないとはいえません。苦労して一人目を出産しましたが育児の大変さを知り、経済的にも育児環境的にも二人目についてどうするか、というのはすごく考えてしまいますね。」
厚生労働省の調査でも、核家族化が進む現代において、育児や家事を一人で担う世帯は年々増加しているとされています。こうした負担は「もう一人子どもを産む余裕がない」と感じさせ、結果として少子化が進み、それがまた高齢化を加速させるという悪循環につながっています。
一方、80歳の地元の方に当時の子育てを聞いてみたところ意外な声が返ってきました。
「昔は祖父母や同居していた家族に子どもを預けられたから、一人で抱え込むことは少なかった。」
「わが子を抱っこして一日ずっと面倒をみるというよりは、田んぼをはじめとする仕事をしていた時間の方が長かったかもしれません。そう感じるくらい、子育てを大変だ!と感じた記憶があまりないですね。」
三世代同居が当たり前だった時代と、核家族化が進んだ現在とでは、子育ての環境が大きく異なっていることがわかります。
移住して地域のママさんや高齢者から直接聞いた声を通じて、自分がもし子育てをする立場なら…と強く想像すると、地方での子育ては「大自然の中で囲まれて子育てができる」などメリットを感じる一方で、その現状は少子高齢化社会の多大な影響があって大変なのだと感じました。もし私が結婚して「子育てをしよう」とした時に、Iターン移住で地域に親戚もいない場合、同じように「ワンオペ育児」をせざるを得ないのはデメリットに感じてしまうかも…というのが正直なところではあります。
特に私はIターン移住で阿東地域に移住してきました。Uターン移住のようにすでに地域に基盤があって、家族や親せきがいる=頼れる存在がいる状況での移住ではありません。なお、Uターン移住のメリットについては別記事でも触れています。
Iターン移住者が語る「Uターン移住」のリアル!そのメリットと秘訣
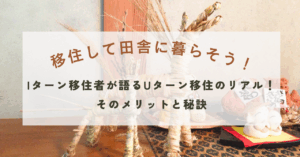
少子高齢化社会の中、三世代同居が見直される理由

少子高齢化社会の中で、近年再び注目されているのが「三世代同居」です。祖父母が育児を支援できれば、子育て世代の負担は大きく減りますし、高齢者にとっても孫との交流が生きがいとなり、孤立の防止にもつながります。さらに、介護の担い手を家族で分担できるメリットもあります。
阿東でも数少ない三世代同居の家庭は、地域行事の中心を担ったり、子どもの世話を手伝ったりと、地域コミュニティを支える存在となっています。しかし一方で、都市部では住宅事情や価値観の変化から「親とは別居したい」と考える若い世帯も多く、三世代同居がすぐに普及するのは難しいのが現実です。
「超」少子高齢化である阿東地域のリアル

阿東には国の重要無形民俗文化財に指定されている「トイトイ」(文化庁「国指定文化財等データベース 地福のトイトイ」)という行事があります。かつては子どもたちが主役でしたが、近年は子どもの数が減り、開催自体が難しくなってきています。文化の継承すら脅かされているのが現実です。昔から続いてきた子供と大人の交流をつなぐ「トイトイ」という地域行事がなくなることは、地域の交流の機会がひとつ失われることを意味するため、とても胸が痛みますね。
地福のトイトイ(国指定の無形重要民俗文化財)
文化庁「国指定文化財等データベース 地福のトイトイ」
1月14日夜、子どもたちが集落の家々を1軒ずつまわり、持参したワラウマ(藁馬)と供物とを交換し、家内安全や無病息災、五穀豊穣などを祈願する小正月の訪問者の行事である。子どもたちは、訪問先の家の前にくると、ワラウマを笊に入れて玄関先に置き、「とい、とーい」と大声で叫び物陰に隠れる。家人がでてきてワラウマを受け取り、代わりに餅や菓子などを笊に入れると、子どもたちは家人に見つからないようにそれを持ち去る。このとき、家人が子どもたちに水を浴びせようとすることもある。(※解説は指定当時のものをもとにしています)
また、教育面を見ても、阿東地域には山口高等学校徳佐分校があったものの、少子化により2025年3月末に閉校となってしまいました。(山口高等学校徳佐分校(山口県教育委員会))多くの子どもは中学を卒業すると地域外の高校へ進学します。そのまま都市部で就職し、地元に戻ってこないケースがほとんどです。結果として地域には高齢者が残り、医療や介護の担い手不足がさらに深刻化しています。隣に住む高齢夫婦から「子どもは街で就職して戻ってこない」と聞いたとき、この構造が根深いことを改めて実感しました。
少子高齢化社会を乗り越える地域の可能性やこれからの取り組み
移住し阿東での生活を通して、少子高齢化社会は数字ではなく日常の風景として私の前に現れました。子どもが少なく、高齢者ばかりの地域で過ごすたびに「この先、地域の未来はどうなるのだろう」という不安もあるものの、家族も親族もいない私でもあたたかく迎え入れてくれた阿東地域で暮らし続けたい思いから「私に何ができるのか」という問いが心に芽生えています。
阿東の姿は日本全体の縮図です。少子高齢化は単なる統計ではなく、日常を大きく変えていく現実です。課題は多いですが、地域には可能性もあります。後続の記事では、阿東で実際に取り組まれている地域包括ケアや移住促進、子育て支援の実践を紹介しながら、少子高齢化とどう向き合うべきかを一緒に考えていきたいと思います。
出典一覧
- United Nations, World Population Prospects 2022
https://population.un.org/wpp/ - 内閣府「高齢化の推移と将来推計」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html - 文化庁「国指定文化財等データベース 地福のトイトイ」
https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/302/00000885 - 山口高等学校徳佐分校(山口県教育委員会)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/29/20230331.html