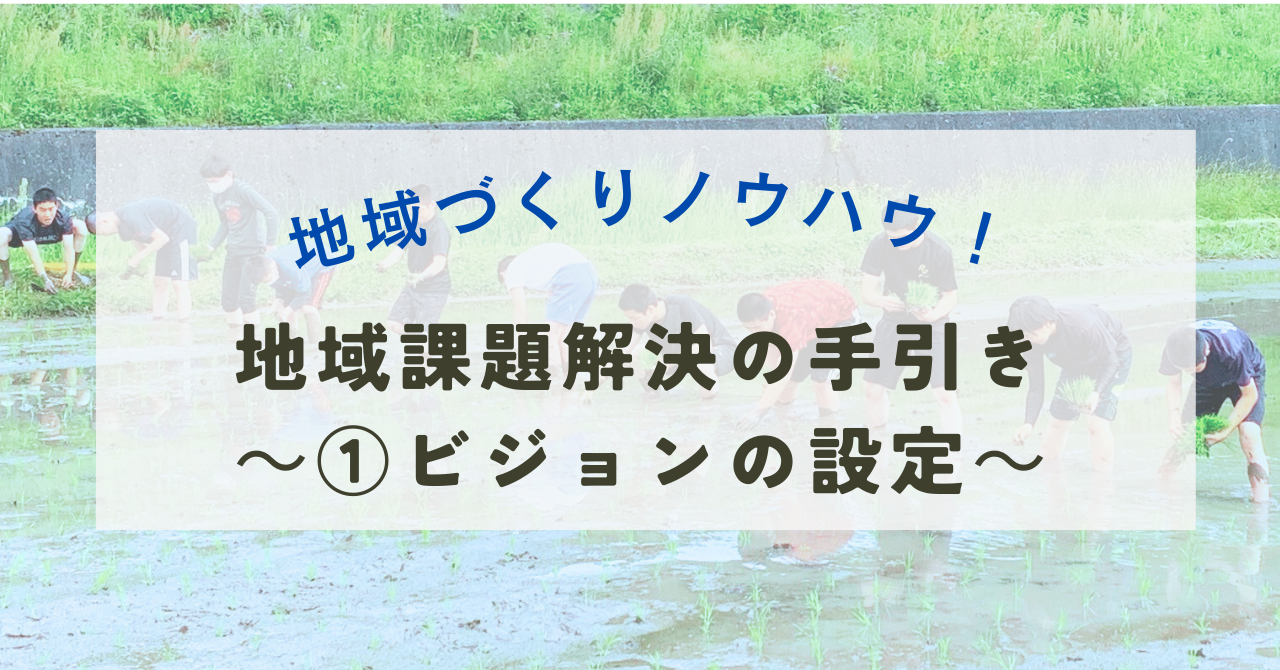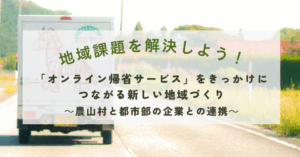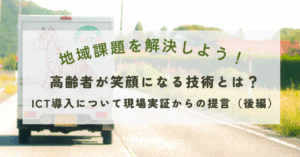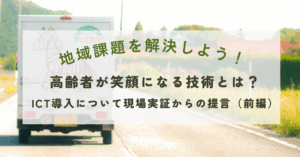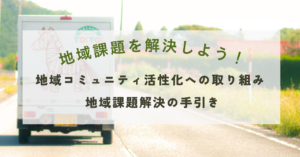高齢化率約60%、少子高齢化が著しく進む山口市阿東。阿東のような過疎化が進む農山村地域では、「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などの地域課題が深刻です。今回は、山口市阿東地福にある「ほほえみの郷トイトイ」事務局長である高田新一郎さんに、地域課題解決の手引きとして、地域づくり・地域課題解決のための取り組みや具体的な方法を伺いました。
地域課題解決の第一歩:ビジョン設定の重要性について
ーー今日は地域課題解決における「ビジョン設定」の重要性について、高田さんに詳しく伺います。よろしくお願いします。
高田 よろしくお願いします。地域づくりの現場では、まずビジョンをしっかり描くことが非常に重要です。地域課題解決に取り組むうえで、行動指針となるのがこの「ビジョン」だからです。この「ビジョンの設定」を疎かにしたまま、地域課題解決のための計画を立ててしまいがちですが、ほとんどの場合が失敗してしまいます。まずは地域住民が「この地域でどうやって暮らしていきたいか」という未来像をもって、そのビジョンのために何ができるかと計画・行動していくことが大事です。
ーーなるほど。地域課題解決のスタートはビジョンからということですね。具体的に、なぜビジョンが必要なのでしょうか?
高田 一言でいうと、ビジョンは「地域の未来像」です。将来どうすればいいか迷ったときに指針となりますし、地域住民ひとりひとり、もちろんさまざまな思いがあるために、時に感情的になり揉めたり、人を批判してしまう場合があります。そんな時に、ビジョンを設定しておくことで感情ではなくビジョンに基づいて説得することができます。特に少子高齢化や人口減少、空き家問題などは地域共通課題ですので、住民が同じ方向を向くためにも不可欠です。
住民主体で描く地域ビジョン策定の上で気を付けるべきこと
ーーなるほど。では、ビジョン設定の際に押さえておくべきポイントはありますか?
高田 いくつかあります。まず、ビジョンは短期的ではなく、長期的視点で設定することが重要です。地域課題は1~2年で解決するものではありません。10年後、20年後の地域がどうなっているかを考えて描く必要があります。
また「地域づくり」と聞くと市や行政のイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも市や行政は地域課題を解決していく上での支援者であって、地域課題の当事者ではないという点も気を付けたいです。
そして、これは地域づくりに限った話ではないかもしれませんが、個人の利益を追求するようなものではいけません。「少子高齢化による担い手不足」「人口減少による生活インフラの衰退」「空き家問題」など多くの地域課題は地域において共通課題となっています。理想の地域の未来像は似ることはあっても、全く同じになることはないでしょう。
地域の未来を地域住民自らが描き、それを達成するためにビジョンを設定します。このビジョンを描くのは国でも、行政でも、地域づくりのコンサルティング会社でもありません。その地域に住む地域住民皆さん自身が描く必要があります。
地域の声を代表するコアメンバーによる意見交換のポイント
ーー住民主体で描く、というのは具体的にどういう方法で進めるのでしょうか?
高田 まずはコアメンバーを選定します。本来ならば、地域住民ひとりひとりの声をビジョン設定の際に盛り込みたいところですが、全員の声を反映することは現実的には難しいので、コアメンバーが地域の意見を代表する形になります。例えば、地域活動に注力している個人や団体、例えば敬老会や婦人会、地域の役員などがコアメンバーとして適任です。
次に、コアメンバーが決まったら意見を出し合いましょう。「地域の未来のために」という思いが前提ですので、正直に意見を出すこと、年齢や立場に関係なくフラットな議論を行うことがポイントです!「今まではこうだった」「昔やったけれどうまくいかなかった」といった、過去の経験談に基づいた意見や、誰かの意見に対してマイナスの意見やダメ出しをすることは絶対にダメ!ではないのですが、地域のビジョンをともに考えていく上ではなるべく忘れましょう。
わかりやすい「キャッチフレーズ」で地域にビジョンを共有
ーーなるほど。コアメンバーが意見をまとめた後はどうするのですか?
高田 集まった意見をもとに、コアメンバーで再度整理してたたき台を作ります。この時、ビジョンを端的に表現できるキャッチフレーズを付けると伝わりやすくなります。例えば、阿東地福のほほえみの郷トイトイでは、ビジョンは「ほほえみの郷トイトイ構想」、キャッチフレーズは「地域の笑顔で作る、笑顔あふれる安心の故郷づくり」です。
ーーキャッチフレーズをつけるとビジョンを地域に伝わりやすくなるわけですね。ちなみに情報共有の面で気をつけることはありますか?
高田 そうですね、ビジョン策定の過程は随時地域に情報発信することが重要です。「知らない間に勝手に決められた!」と感じられないよう、進行状況や議論内容を共有します。市や行政ではここまでリアルタイムで行うことは難しいので、住民主体の情報共有がポイントですね。
支援者である行政・自治体との協働の進め方
ーー行政との関わり方も気になります。どこまで住民主導で、どこから行政支援を受けるべきでしょうか?
高田 あくまでも行政や自治体は支援者です。予算や制度面の協力を得るのは大切ですが、できることは住民主導で行います。また、行政からの予算取りは計画的に行い、その効果を示すことが信頼構築につながります。地域課題解決には、住民主体の実行力と行政の支援を組み合わせることが不可欠です。
ビジョンを明確にして次ステップ:アクションプラン策定へ
ーー最後に、地域課題解決の取り組みを始める意義について教えてください。
高田 地域課題の深刻さを理解するには、統計や数値的データが不可欠です。人口減少や少子高齢化の将来予測を示し、「取り組むか取り組まないか」で地域の未来に差が生まれることを伝えます。一度失うと取り戻すのは大変ですので、早期に取り組むことが重要です。
ーー非常に参考になりました。地域課題解決の第一歩は、やはりビジョンを住民主体で描くことなのですね!
高田 その通りですね。地域住民自身が未来像を描き、明確なビジョンを行動指針として設定することで、地域課題に体系的に取り組むことができます。私の経験上、今までと全くことなる唐突なビジョンが設定されることはなく、自然と地域の描く未来像がビジョンとして設定されています。「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などさまざまな地域課題がありますが、ビジョンやその対策・解決策は地域ごとに特色がでるでしょう。
地域で「地域の未来像」を一番解像度高く描けるのは、その地域に暮らす皆さん自身だけだと思っています。持続可能な地域づくりのため、「地域の未来像」であるビジョンを設定して地域課題解決に向けて歩き出すヒントがこの記事を通して見つけるきっかけとなれば幸いです。
ーーありがとうございました!次回の記事では、ビジョンをもとに「アクションプランの作成」について伺う予定です。お楽しみに!
地域課題解決の手引き:ビジョン設定の要点まとめ
地域づくりを進める上で押さえておきたい、ビジョン設定の要点をまとめました。ぜひ、みなさんの地域課題解決や地域づくりの中で役立つヒントになれば幸いです!
- 地域課題解決の第一歩はビジョン設定
- ビジョンは長期的視点で、地域住民自身が描く
- コアメンバーによる意見交換とフラットな議論が重要
- キャッチフレーズを付けて地域にわかりやすく共有
- 行政・自治体との協働は支援を受けつつ、住民主導で実行
- ビジョンは明確に!そうすれば方向性を見失わず、次のステップであるアクションプラン策定もスムーズ
次のステップ:具体的なアクションプラン策定
ビジョン設定の次に行うべきは具体的なアクションプラン策定です。詳細は下記の記事で紹介しています。
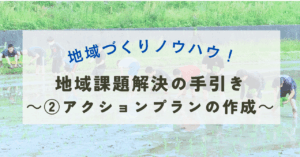
ビジョンをもとに課題を整理し、優先順位をつけて計画を立てる方法を学べます!
地域課題解決の手引き ~③コミュニティ動員と、モチベーション向上~
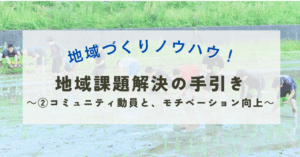
ビジョンを共有し、地域住民の共感を得ながら活動を広げるポイントを解説していますよ。

地域住民が一丸となったら、どうやって予算や補助金制度に関する連携を自治体や市町村ととっていくかについて解説しています。
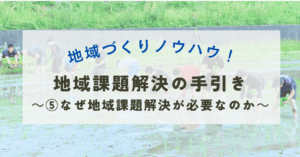
地域課題の手引きとしてステップをお伝えしてきましたが、そもそもなぜ地域課題が必要なのかについて解説しています。
また、地域活動の課題をプロと一緒に解決したい方は、コミュニティ・コンサルティングのご案内はこちらをご覧ください。