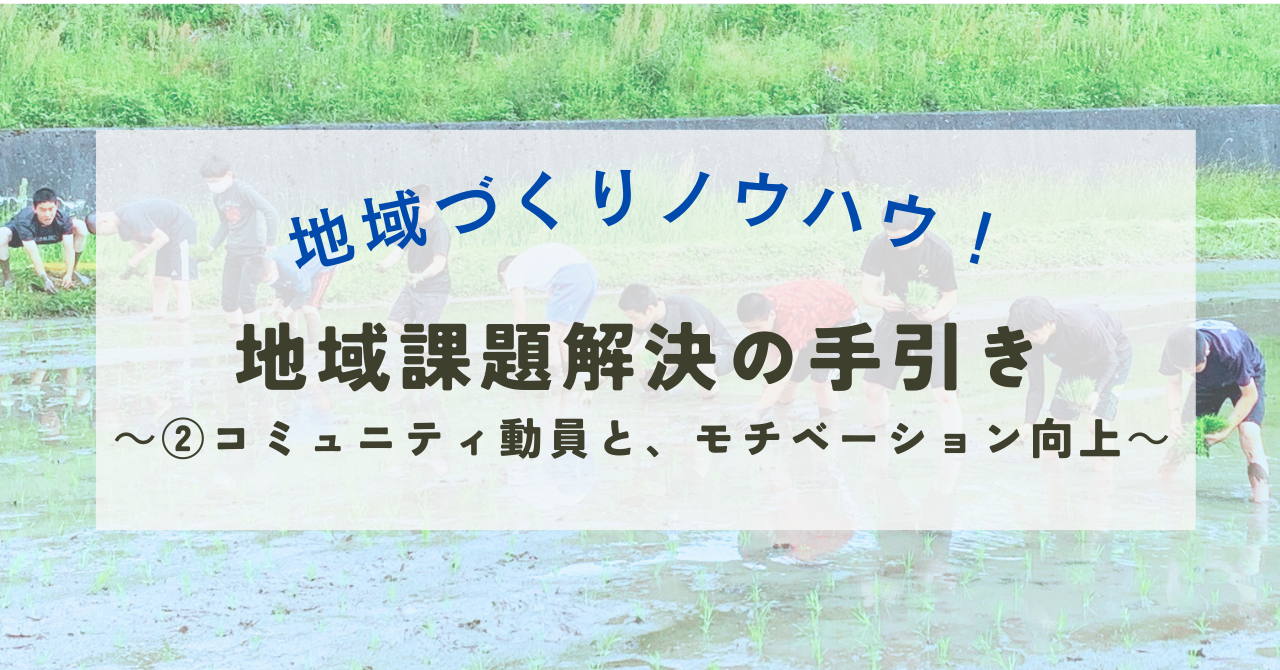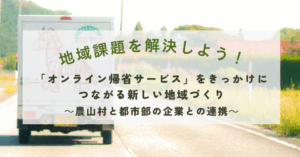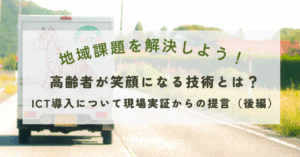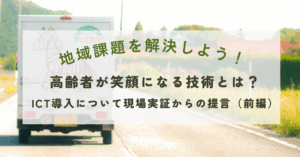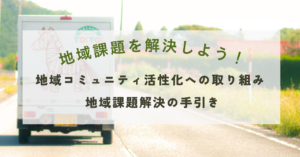高齢化率約60%、少子高齢化が著しく進む山口市阿東。阿東のような過疎化が進む農山村地域では、「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などの地域課題が深刻です。今回は、山口市阿東地福にある「ほほえみの郷トイトイ」事務局長である高田新一郎さんに、地域課題解決の手引きとして、地域づくり・地域課題解決のための取り組みや具体的な方法を伺いました。この記事ではステップ3「コミュニティ動員と、モチベーション向上」についてお話いただきます。
地域で地域課題解決策をアクションする際の課題
ーー それではさっそくお話を伺っていきたいのですが…ビジョンの設定、そしてビジョンへ進むためのアクションプラン作成、そしていよいよ次は地域で実際にアクション(実行)をしていく!という段階ですが…これを実行していく時の課題はありますか?
高田 やはり、住民の皆さんをどう巻き込むかが一番の課題ですね。たとえば、ビジョンやアクションプランを提示しても、「そうだね、やろう!」とすぐに動き出す地域の方は少ないです。むしろ、「これってどうなの?」という疑問や戸惑いの声が上がることが多いですね。何事も最初から順調に進むことはまずありません。
地域づくりコンサルから見た住民巻き込みのポイント
ーー そうした場合、どのように地域の方を巻き込むため対応されているのですか?
高田 いくつかポイントがあります。まず、私たちが考えるビジョンは、地域をより良くするための目標であり、住民の皆さんのためであることをしっかり伝えます。そして、「地域社会は住民が所属して初めて成り立つ」という基本的な視点に立ち、自分たちが暮らす地域の環境が良くなれば自分たちにとってもプラスだという点を共有します。さらに、地域活動を「楽しむこと」を大切にしています。
地域課題解決のため「楽しむ」というアプローチ
ーー「楽しむこと」とは具体的にどういうアプローチですか?
高田 「地域づくりをしましょう!」と堅苦しく呼びかけるのではなく…「地域で楽しいことをやりましょう」と企画・実行して、「やって楽しかったね!」と体感してもらい、「もっと楽しくするには?」と次へつなげていく…というように段階を踏んでいくことが必要です。たとえば、地域でイベントを開催し、それが楽しいと感じてもらえれば「次はもっとこうしたらいいんじゃないか」と地域住民側から自然と声があがって、次のステップにつながっていくイメージです。
コミュニティ動員時の失敗例と注意点
ーー 逆に、失敗例や注意点などはありますか?
高田 ありがちなのは、「ある団体が決めたことだから、こうあるべき」という提言を押し付けてしまうことです。この場合、住民の思いが反映されず、地域住民の本音とはずれた方向に進んでしまいます。また、キラキラと見栄えだけが立派なアクションプランを掲げても、そこに「共感」がなければ地域住民にとって心に響かないことがほとんどです。地域コミュニティーである地域住民を巻き込むためには、「たしかに」「そうだよね」と共感できる要素をビジョンやプランの中にちりばめる必要があります。
地域課題解決のための小さな一歩の重要性
ーー この「共感」できる要素については、はどの地域で取り組む際にも共通していえることですね。でも、地域づくりのためのビジョンは壮大になりやすいイメージがあって、地域住民の方ひとりひとりが「そういわれても、どんなこと?」という風にとっつきにくい時もある気がします。大きなビジョンから、地域に落とし込んでいく場合、どのようにしていけばいいでしょうか?
高田 これは適材適所の声かけが重要ですね。たとえば、生涯学習や健康増進、地域のイベントで料理をつくるボランティアなどさまざまな活動をする婦人会へ「このイベントで豚汁を作るお手伝いをお願いしたい」と婦人会に話を持ちかけるように、各カテゴリーの住民に響くテーマをビジョンの中の細かい中から選びます。
この声かけをしていくためには、予め地域の内情や団体の特性を把握しておくことが大切です。また、各団体のコアとなるメンバーを先に見つけ、2~3割でも賛同してくれる人を巻き込むことで、その人たちが他の住民を引っ張ってくれることがあります。そうしてひとりからふたり、ふたりから三人へと波及していくことで地域全体へつながっていきます。
地域住民のモチベーション向上ポイント
ーー 地域住民のモチベーション向上を成功させるためのポイントをさらに詳しく教えてください。
- 短期間のアクションを繰り返す:小さな一歩から踏みだし、それを繰り返していくことで短期間で成果が見えやすく、住民のモチベーションを維持することができます。
- 失敗事例やリスクの提示:すべてのアクションが必ず成功するわけではない、というように事前に課題を共有して失敗することもあるよ、と失敗事例を提示してリスクヘッジを行います。
- 住民の主体性を尊重:アクションプランを作るのはコアメンバーですが、実際に動くとなると主体になるのは住民の皆さん自身です。地域住民の中にある「こうありたい」という内発的な意欲を引き出すことが重要です。
- 適材適所のリーダーシップ:住民全員を一度に巻き込むのではなく、まずは団体や組織の中から意欲的に協力してくれそうなコアメンバーを見つける。そして、そのメンバーを通じて巻き込む範囲を広げていくことで、波紋のように活動を広げていくイメージです。
地域づくりの成功は「相互扶助」と楽しさが鍵
ーー 10年、20年後のビジョンを掲げて地域づくりをしていくわけですから、地域のモチベーションの維持・向上は必須ですね。非常に参考になります!
高田 地域活動は一人で抱え込む必要はありませんし、というかそもそも一人でできるものではありません。「相互扶助」の精神があるからこそ、住民の意見を聞きながら、一歩ずつ進めていくことで、大きな成果につながります。そして、活動そのものを楽しむことが、結果として住民の意欲を引き出し、持続可能な地域づくりに結びつきます。
地域課題解決に取り組む仲間を見つけ、ビジョンを成し遂げよう
ーー 大きな一歩も、細分化してみてみたら地域住民の皆さんの小さな一歩で成り立っていることに気付きますね!桃太郎も一人では鬼と戦えなくても、仲間がひとり、またひとりで増えていったからこそ、最終的に鬼退治(ビジョン)を成し遂げられたわけですもんね!
高田 地域づくりや課題解決って堅苦しいイメージがあると思いますが、それは逆に言えば課題解決をした先に、目指すビジョンに近づいていけるということです。
ーー 楽しく地域課題解決のために小さなことでも取り組める気がしてきました!今回も貴重なお話、ありがとうございました。
高田 ありがとうございました。
地域課題解決の手引き:コミュニティ動員と、モチベーション向上の要点まとめ
地域づくりを進める上で押さえておきたい、コミュニティ動員とモチベーション向上の要点をまとめました。ぜひ、みなさんの地域課題解決や地域づくりの中で役立つヒントになれば幸いです!
- 地域課題の解決には、住民の主体的な参加が不可欠。
- そのために必要なのは「コミュニティ動員」と「モチベーションの向上」。
- 成功の鍵は、住民が「自分ごと化」して「楽しく」取り組める仕組みづくり。
- 行政やリーダーは、目標を共有し、小さな成功体験を積み上げることが大切。
- 信頼関係の構築と共感を生むコミュニケーションが、継続の原動力になる。
次のステップ:行政・自治体との関わり方
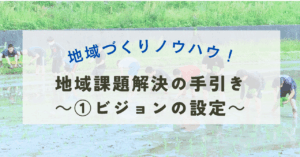
地域課題解決のための第一歩!とても重要な「地域課題解決のための指針」となるビジョンの設定について解説しています。
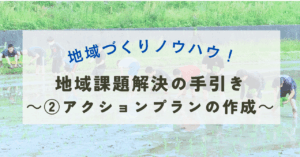
ビジョンの設定ができたら、どう地域にビジョンを落とし込んで行動していくかについて学べます!

地域住民が一体となったら、予算や補助金制度など自治体や市町村との連携をどうするかについて解説しています。
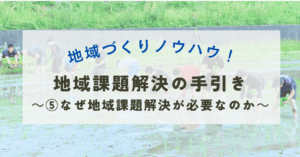
地域課題の手引きとしてステップをお伝えしてきましたが、そもそもなぜ地域課題が必要なのかについて解説しています。
また、「自分たちのの地域でも何か始めたい」と思ったら、まちづくり支援の詳細ページをチェックしてみてください。