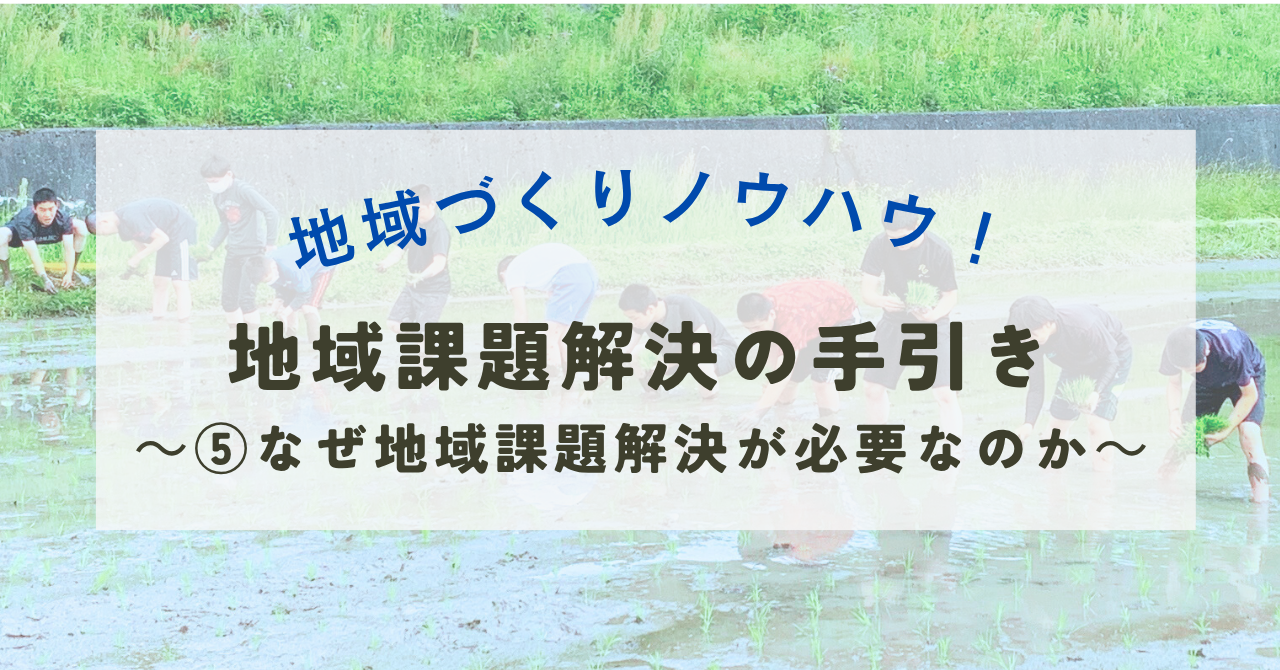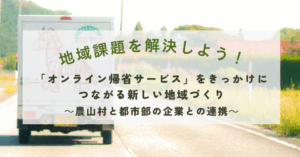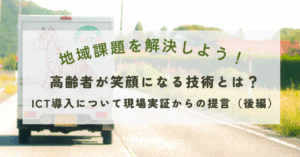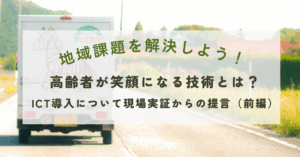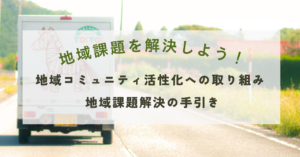高齢化率約60%、少子高齢化が著しく進む山口市阿東。阿東のような過疎化が進む農山村地域では、「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などの地域課題が深刻です。今回は、山口市阿東地福にある「ほほえみの郷トイトイ」事務局長である高田新一郎さんに、地域課題解決の手引きとして、地域づくり・地域課題解決のための取り組みや具体的な方法を伺いました。この記事ではステップ5「なぜ地域課題解決が必要なのか」についてお話いただきます。
なぜ地域課題解決が必要なのか?
人口減少・少子高齢化がもたらす現実
ーー 高田さん、本日はなぜ地域課題解決に取り組むのか、についてお話を伺いたいと思います。まず、地域課題解決に働きかける必要性をどのように感じていらっしゃいますか?
高田 地域課題については、特に人口減少や少子高齢化といった問題があり、それを地域の方も重々承知だと思いますが、地域課題を取り組む上で多くの人が「知っているけれど実感がない」という状況が深刻だと思います。「現状はなんとなくわかっているけど…」と漠然としていたり、「現在語られている地域課題について、将来を見据えて考えていない(考えられない)」など危機感が薄い場合が多いですね。当事者のひとりでありながら、どこか課題が他人事のように捉えられがちです。
しかし、実際にはそう遠くない将来には確実に今より地域の人口が減り、少子高齢化が進むことで、皆さんにとってこの地域での暮らしが大きく変わる時期が必ず訪れることは間違いないでしょう。「地域課題解決」の重要性というのは全国の地方自治体でいえることだと思います。
地域課題を“自分ごと”にするための第一歩
ーー 確かに、課題の深刻さを頭ではわかっていてもよくわからない難しい!どうすればいいかわからない!という声をよく耳にします。そうした場合には、どのように働きかけていくのがいいでしょうか?
高田 ただ「人口減少」「少子高齢化」といっても漠然としているので、統計やデータといった数値的な根拠を活用して、地域の現状や将来予測を明確に伝えることが大切ですね。例えば、「現在の人口がこのまま減少すると、20年後には半分以下になる」「人口減少により、地域の生活圏にあるもの(スーパー、コンビニなどのインフラ)が経営が維持できずに撤退する」など具体的な根拠をもとに現在と未来を示すことで、多くの人が「このままではいけない」とおのずと実感するようになります。
ーー それでも、「今、目の前の生活に影響がないから大丈夫」「と感じる人も多いように思います。その点についてはいかがでしょうか?
高田 そうですね。ただ、そこで考えるべきなのは、「今の課題解決が解決されずにいたら、地域の未来をどう変えるのか」を見据えたアクションを、地域のひとりひとりが小さなことからでも考えてアクションを起こすことです。現在から数年後といった目先の改善だけではなく、次の世代が生きる10年後、20年後の地域の持続可能性を見据えた取り組みが必要だと思っています。今、地域の課題を知って危機感を覚えて、なにか小さなアクションでも起こしている地域と、何もせず現状を放置している地域とでは、将来的に大きな「格差」が生まれるでしょう。
行動する地域と、しない地域の「格差」
ーー 「格差」という言葉が出ましたが、それがどういう形で現れるのか、具体的に教えていただけますか?
高田 例えば、積極的に地域課題に取り組み、地域に興味を持ってもらおうと頑張っている地域では、地域に興味をもって外からの移住者が増えたり、地域の魅力が高まったりといったポジティブな変化が期待できます。一方で、「どうすればいいのだろう」と悩むだけで行動を起こさず課題をおざなりにした地域では、地域に興味を持ったりする人が少なく、人口減少がさらに進み、結果的に学校や医療施設の廃止、交通・商業インフラの崩壊といったネガティブな連鎖が起こる可能性がありますね。失ってから取り戻すのは大変ですよね。
地域課題解決の最初の一歩
ーー なるほど、それは確かに大きな違いですね。小さな一歩が、大きな将来を支えるのであれば、地域の方ひとりひとりが「地域づくり」や「地域課題解決」に対して危機感をもって、高田さんが考える「地域課題解決の最初の一歩」とは何でしょうか?
高田 まずは、自分たちの地域が直面している現状を知ることだと思います。そして、何でもいいから小さなアクションから始めること!たとえば、地元のイベントに参加したり、何気ない井戸端会議でもいいし、地域団体の集まりなどで地域の課題について話し合う場を設けるといったことでも良いと思います。暮らす地域の未来を想像しながら、日々少しずつでも行動を重ねていくことが大切です。
ーー 本日は貴重なお話をありがとうございました。これからの地域づくりのヒントになればいいですね。
高田 将来の地域のために、地域のひとりひとりが一丸となって未来について考えていきましょう!
阿東地域に学ぶ、課題解決のヒントと小さな一歩
シリーズでお届けしてきた「地域課題解決の手引き」も、いよいよ最終回です。
これまでの連載では、阿東地域の事例を通して、人口減少や少子高齢化など、地域が抱えるさまざまな課題と向き合うヒントを紹介してきました。
地域課題の解決は、行政や特別な団体だけの仕事ではありません。
暮らす地域をより良くしていくためには、一人ひとりの小さな行動が何より大切です。
「声をあげる」「声を集める」「アクションを起こす」――この3つのステップが、未来を変える大きな一歩につながります。
たとえば、地域のイベントや話し合いの場に参加してみる、身近な課題をSNSや友人と共有してみるなど、できることから始めてみましょう。その小さな行動が、やがて地域全体を動かす力になります。
阿東地域のように、住民一人ひとりが課題を自分ごととして捉え、行動を重ねていくことが、持続可能な地域づくりのカギです。あなたの地域でも、今日からできることを見つけて、一緒に未来をつくっていきませんか?
地域課題解決の手引き:なぜ地域課題解決が必要なのかの要点まとめ
地域づくりを進める上で押さえておきたい、地域課題に取り組むのは何の為か?についての要点をまとめました。ぜひ、みなさんの地域課題解決や地域づくりの中で役立つヒントになれば幸いです!
- 人口減少・少子高齢化が進行し、地域の生活環境が変化するのは確実
- 多くの人が課題を「知ってはいるが実感していない」状態にある
- 統計データを活用し、現状と将来を可視化することで危機感を共有
- 今の行動が10年後・20年後の地域の持続可能性を左右する
- 行動する地域と放置する地域で、将来に大きな「格差」が生まれる
- 小さなアクション(参加・対話・発信)から始めることが重要
- 一人ひとりの意識と行動が地域の未来を変える力になる
地域課題解決の手引きを地域づくりに生かし、課題解決へ!
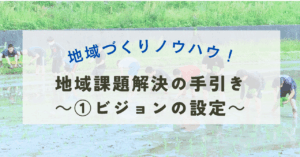
地域課題解決のための第一歩!とても重要な「地域課題解決のための指針」となるビジョンの設定について解説しています。
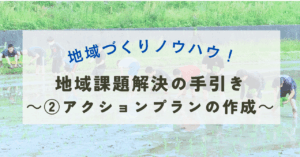
ビジョンの設定ができたら、どう地域にビジョンを落とし込んで行動していくかについて学べます!
地域課題解決の手引き ~③コミュニティ動員と、モチベーション向上~
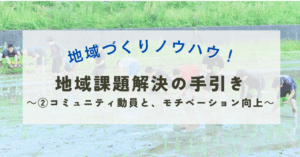
ビジョン、アクションプランが出来上がったらどう地域「巻き込む」か、そして地域課題解

地域住民が一体となったら、予算や補助金制度など自治体や市町村との連携をどうするかについて解説しています。
また、「自分たちのの地域でも何か始めたい」と思ったら、まちづくり支援の詳細ページをチェックしてみてください。