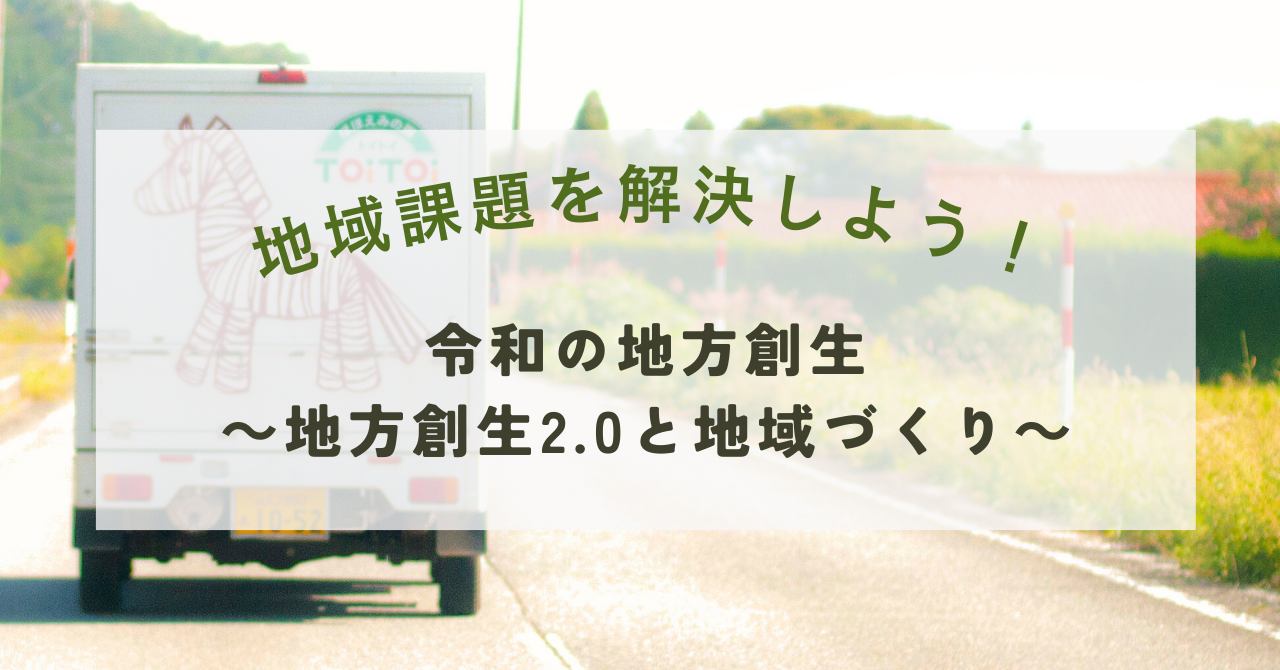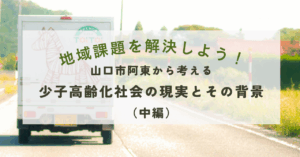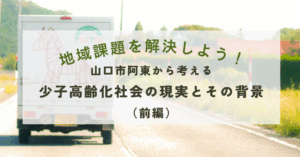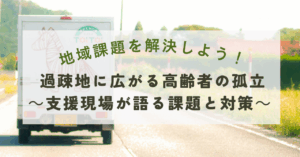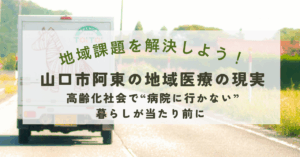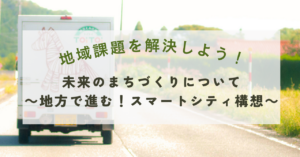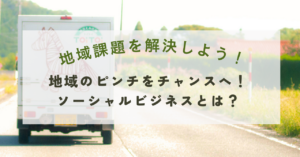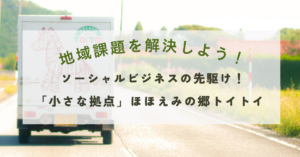こんにちは、まつきおです!日本の地方は今、大きな転換点に立っているとされています。令和の時代に「社会的課題」といわれる人口減少、少子高齢化、若者の都市部への流出、地域経済の疲弊などなど、日本が抱えている課題は深刻化しています。しかし、こうした現状に立ち向かい、地方から希望ある未来を見出そうとするのが「地方創生」です。
わたしが地域おこし協力隊として、さまざまな取り組みを行う地方自治体の空き家再生、都市圏との連携プロジェクト、地域内起業の支援など、地域課題解決に対する取り組みについて、視察などで実際に足を運び実感したのは、「地方には地域の課題を未来の希望を切り拓く隠れた可能性がある」ということです。
皆さんご存知の通り、令和6年10月から石破内閣が発足しましたね!その石破総理大臣が掲げる政策の中に「地方創生2.0」があり、「知っていますよ!」という方も多いのではないでしょうか?この記事では「地方創生」、そして石破総理大臣の政策「地方創生2.0」について今後どのように地域づくりに影響していくのかなどに迫っていきたいと思います!
地方創生の歴史
まず「地方創生」という言葉が広く使われるようになったのは平成26年(2014年)、当時の安倍総理大臣が「まち・ひと・しごと創生本部」を設置したのがきっかけです。この動きは、東京一極集中を是正し、地域が自立して持続可能な成長を遂げられるようにすることを目的としたものでした。
「まち・ひと・しごと創生法」
もちろん、地方の衰退は突然始まったわけではありません!戦後の高度経済成長期以降、都市への人口集中が続き、地方では若者の流出と高齢化が進んだ結果…地域の中心であった商店街や農林水産業も衰退したことで、地域の集落そのものが消滅の危機に瀕するようになりました。人口減少により過疎化した地域の地方自治体は財政面でも苦しくなり、インフラの維持すら困難になるケースも増えるようになっていったのです。
このような背景の中で打ち出された地方創生政策は、補助金や交付金による支援と、地方ごとの「総合戦略」の策定を柱とするものでした。これがまさに、地方が「自らの未来を自らの手で描く」ことを後押しする第一歩だったのです。
石破総理大臣と政策「地方創生2.0」
この「地方創生」の旗振り役として大きな役割を果たしたのが、当時の地方創生担当大臣であった石破氏です。彼は防衛や農政といった多分野での政治経験を活かして、地方のリアルな現場を政策に反映していったのです。
そんな石破氏が平成から令和へ時代が変わり、総理大臣となった現在、提唱した新たな概念が「地方創生2.0」です。地方創生1.0が「制度の整備」と「資金の投入」による基盤づくりであったのに対し、2.0はより内面的で創造的な取り組みを重視しています。つまり、外からの支援だけに頼らず、地域の中から変化と価値を生み出すこと。「自立と共創」の精神が、地方創生2.0の本質とされています。
地方創生2.0の5本柱とは
地域がこれから持続可能な地域として地域を発展させるために、5つの重点的な取り組みが掲げられています。
1. 安心して働けて暮らせる、魅力ある生活の場をつくること
地方に移住したいと思っても、「ちゃんと働けるの?」「生活しやすいの?」と不安に思う方も多いですよね。そこで大事になるのが、働き方の見直しや賃金アップ、そして保育や医療など生活の安心につながるサービスの充実です。
石破氏は、「楽しく働けて、暮らしやすい」地方を目指しています。特に若者や女性が「ここに住みたい!」と思えるような環境づくりが、これからの地方には必要なんです。
2. 東京への過度な一極集中を見直すこと
災害や感染症などのリスクを考えたとき、すべてが東京に集中している状態は、実はとても危ういんですよね。だからこそ、企業や大学、さらには政府機関を地方にも分散させる必要があります。
人や情報、仕事が地方にもしっかりと流れるようになれば、それぞれの地域に活気が生まれます。「地方は補完」ではなく「もう一つの中心」として位置づけるべき時代なのです。
3. 地域の魅力を活かした高付加価値な経済づくり
地方には、自然、伝統文化、食、芸術など、独自の「宝物」がたくさんあります。それをただ消費するだけでなく、現代的な感性で新しい商品やサービスとして生まれ変わらせていくことが大切です。
たとえば、伝統工芸を現代風にアレンジしたライフスタイルブランドや、里山の魅力を活かしたエコツーリズムなどがこれにあたります。こうした取り組みが、地域経済を「高付加価値型」に進化させる力になるのです!
4. デジタルや新しい技術をフルに活かすこと
今や、デジタル技術は都市だけのものではありません。地方こそ、リモートワーク、オンライン教育、スマート農業など、新しい技術で暮らしを変えていけるフィールドなのではないでしょうか。特に、ブロックチェーン、DX(デジタル変革)、GX(環境配慮と経済成長の両立)などの新技術を導入すれば、地方の課題(ピンチ)もチャンスに変わります。「ITに弱いから…」とためらわずに、地域こそ最先端に挑戦する時代ですよね。
5. 地域を支えるあらゆる人たちの力をつなげる
「産官学金労言」とは、それぞれ以下のような人たちを指しています
産:企業
官:自治体などの行政機関
学:大学や研究機関
金:金融機関(銀行など)
労:労働組合や働く人たち
言:地域メディアや市民の声
この6者がしっかり連携して、同じ目標に向かって協力することが、地方の本当の底力を引き出すカギというわけです。自治体同士の横のつながりもとても重要で、近隣市町村が一緒にプロジェクトを動かせば、より大きな成果が期待できますよね!
課題解決型から価値創造型へ
従来は「人口減少を止める」「経済を支える」といったマイナスの補填が目的でしたが、これからは「地方にしかない価値を発信する」「新しい生き方・働き方を提案する」といった創造的なアプローチが求められます。石破氏は、地方を「国の未来を切り開く先進地域」として位置づけています。都市の効率性に対し、地方の多様性・文化・自然との共生は、これからの時代に欠かせない資源なのだと語っています。
私たちができること
阿東地域でも日々感じているのは、「本気で取り組む人が一人いるだけで、地域は動き出す」という事です。これは阿東地域に限らず、これからの地域づくりや未来を考えアクションを起こしている地域は、すでに動き出していると感じます。たとえば、阿東地域で廃校になった小学校を一部リノベーションしてコワーキングスペースに変えるなど、かつて活用されていたが使われなくなり負の財産となっている場所が、今では移住者や地域の若者が集うきっかけになっています。そこに必要なのは、必ずしも巨額の資金や政治力ではなく、「信じて動く人の存在」があったからこそ。
地域づくりには時間がかかりますし、必ずしもすぐに成果が見えるわけではありません。でも、小さなチャレンジの積み重ねが、やがて大きな波を生むんですよね。
地方創生と未来のまちづくり
自分の暮らす地域に誇りを持ち、その可能性を信じ、他人任せにせずに未来を共に創っていく——そんな姿勢が、次の時代の地方を形作っていくのではないでしょうか。これからの地方は、「支援される対象」ではなく、「価値を生み出す発信地」として再定義されていくのではないかと感じます。