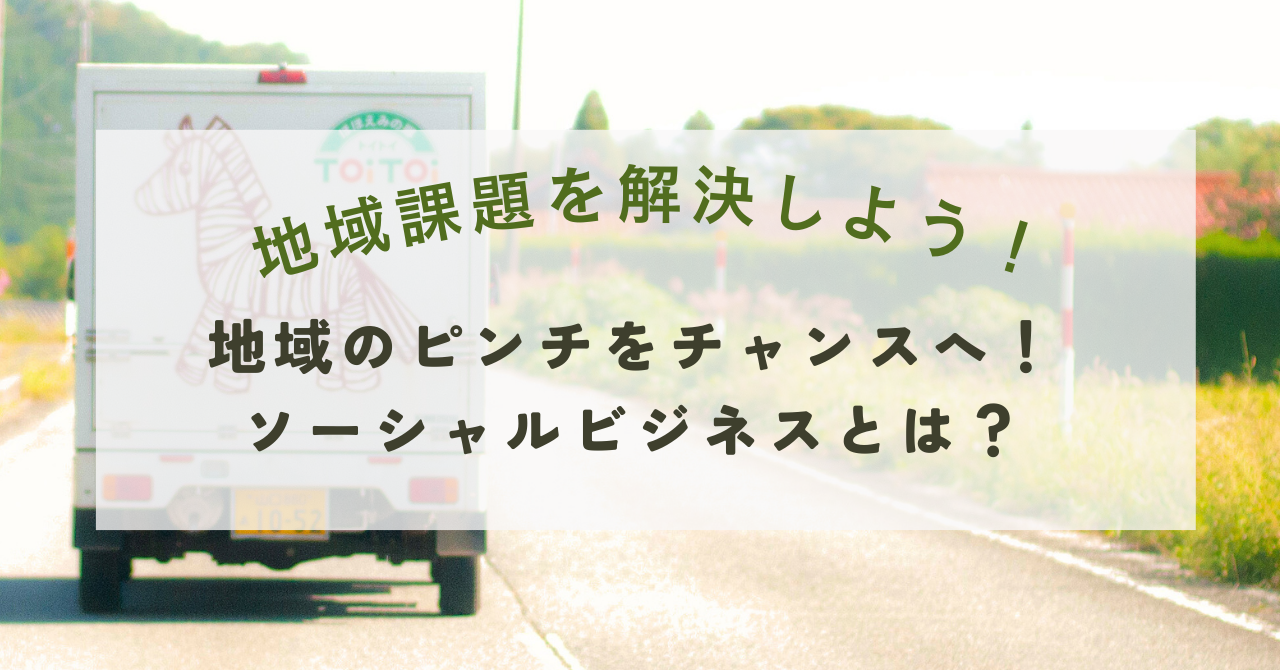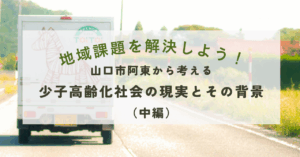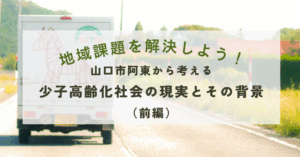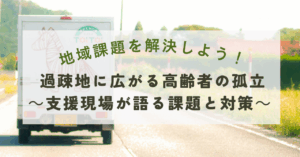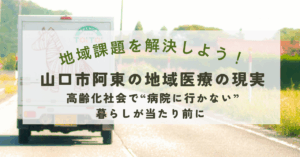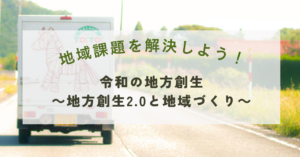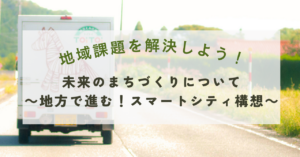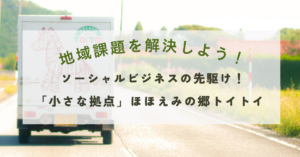こんにちは!まつきおです!皆さんは「ソーシャルビジネス」という言葉をご存知ですか?
東京で日々暮らしている中では「ソーシャルビジネス」という言葉は正直聞いたことがありませんでした!しかし、こうして地域おこし協力隊となり、地域づくりや地域活性化の取り組みについて知ると、地方に限らず日本全体で、「ソーシャルビジネス」で社会的課題を解決を目的とし、持続可能なビジネスとして成立するように利益をあげる事業のあり方が求められるのではないか、と感じています。
この記事ではそもそも「ソーシャルビジネス」って何なん?というところを説明するとともに、事例なども交えてご紹介していこうと思います!
ソーシャルビジネス(コミュニティビジネス)って、何なん?
まず、ソーシャルビジネス(またの名をコミュニティビジネス)って、何なん?ソーシャルビジネスとは…!
社会的課題を解決することを目的としながら、ビジネスの手法を取り入れて持続的に運営される事業のこと。単なるボランティア活動とは違って、収益を上げながら、地域の実情に合ったサービスや商品を提供する。事業を運営する中で地域・住民とともに成長していくことで、地域全体の活性化にもつながる。
日本では、経済省のソーシャルビジネス推進研究会の報告資料による定義は、以下の要件を満たす事業がソーシャルビジネスのと定義されています。
- 社会性:現在解決が求められる社会課題に取り組むことを事業活動のミッションとすること。※解決すべき社会的課題の内容により、活動範囲に地域性が生じる場合もあるが、地域性の有無はソーシャルビジネスの基準には含めない。
- 事業性:ミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。
- 革新性:新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組を開発すること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。
ビジネスとソーシャルビジネスの違いとは
「ソーシャルビジネス」という言葉はすでに10年前より存在していましたが、現代とビジネスのあり方のひとつとして当たり前になってきたのはつい最近だといわれてます。でも、ソーシャルビジネスって私たちが日々口にしている「ビジネス」とは何が違うのか?皆さんご存知ですか?
目的
- 一般的なビジネスは「利益の最大化」を目的とし、顧客に価値を提供することで収益を得る仕組みを構築。
- ソーシャルビジネスは「社会課題の解決」を主目的とし、収益を上げながら持続可能な形で課題解決に取り組む。
収益の活用
- 一般的なビジネスでは利益が株主や投資家への配当に回る。
- ソーシャルビジネスでは利益を再投資や社員の福利厚生に充て、社会的価値の創出に活用。
活動内容
- 一般的なビジネスは市場ニーズに基づいた商品やサービスを提供。
- ソーシャルビジネスは貧困、環境問題、教育など具体的な社会課題の解決に焦点を当てた事業を展開。
持続性
- ソーシャルビジネスは寄付や助成金に依存せず、自立的・持続可能な形で事業を運営する点が特徴。
「貧困・格差」「人口問題」「労働」「健康・医療」「社会的不平等」「食糧・自給率」など…、世界各国で社会的課題は他人事ではなくなっています。もちろん日本も例外ではなく、様々な社会的課題に直面していますよね。
少子高齢化による人口構造の変化は、社会保障制度に大きな圧力をかけており、労働力不足や地方の過疎化にもつながっています。経済格差の拡大は、特にひとり親世帯や若者の間で貧困問題を深刻化させています。また、都市部への人口集中は、地方の衰退を加速させる一方で、大都市圏では住宅問題や通勤ラッシュなどの課題を生んでいます。さらに、頻発する自然災害への対策や、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化対策も重要な課題です。
これらの多岐にわたる社会的課題に対して、政府、企業、市民社会が協力して取り組むことが求められています。こうした社会的課題に対してアクションをおこす場合、一般的なビジネスではなく、地方だからこそソーシャルビジネスであるべき!(と思うくらい)ぴったりなんです!
ピンチをチャンスに変える!地方だから「ソーシャルビジネス」
地方において一般的なビジネスよりもソーシャルビジネスを推進すべき理由は、地域が抱える社会的課題の解決に直結する点にあります。過疎化や高齢化、雇用不足といった地方特有の問題に対して、ソーシャルビジネスは地域住民の生活を支える財やサービスを提供し、地域の維持や再生に貢献します。また、地域内での生産と消費を促進することで、地域経済が循環しやすくなり、新たな雇用創出にもつながります。さらに、地域住民自身が主体となり、地域資源を活用した内発的発展を目指すため、持続可能な地域づくりが実現します。
ソーシャルビジネスはまた、高齢者や主婦など従来の労働市場で活躍しづらかった層も含め、多様な人材が参加できる仕組みを提供するため、社会全体での包摂性を高める効果があります。さらに、地方自治体との連携が進みやすく、補助金や税制優遇などの制度を活用しながら、地域全体で課題解決を図ることが可能です。このように、利益追求型の一般ビジネスとは異なり、地域社会への貢献と持続可能性を重視したソーシャルビジネスは、地方における重要な取り組みとして推奨されます。
社会的課題、地域課題はは乗り越えなければならない「大きな壁」のように思えるかもしれませんが、逆にビジネスとして昇華してプラスへ変えることで、地域課題も持続可能な町づくりへつなげられる「大きなチャンス」でもあるわけです!そう考えたら、わくわくしてきませんか?ただの主婦でも、地域のニーズを洗い出して解像度をあげ、そこに的確にアプローチできたら…利益を生み出し地域の課題も解決でき、持続可能なビジネスができるかも…!?
みなさんの地域でも、始まっているかもしれないソーシャルビジネス。今後のソーシャルビジネスや地方の課題解決のための動向についても注目ですね!