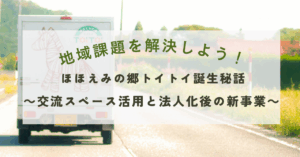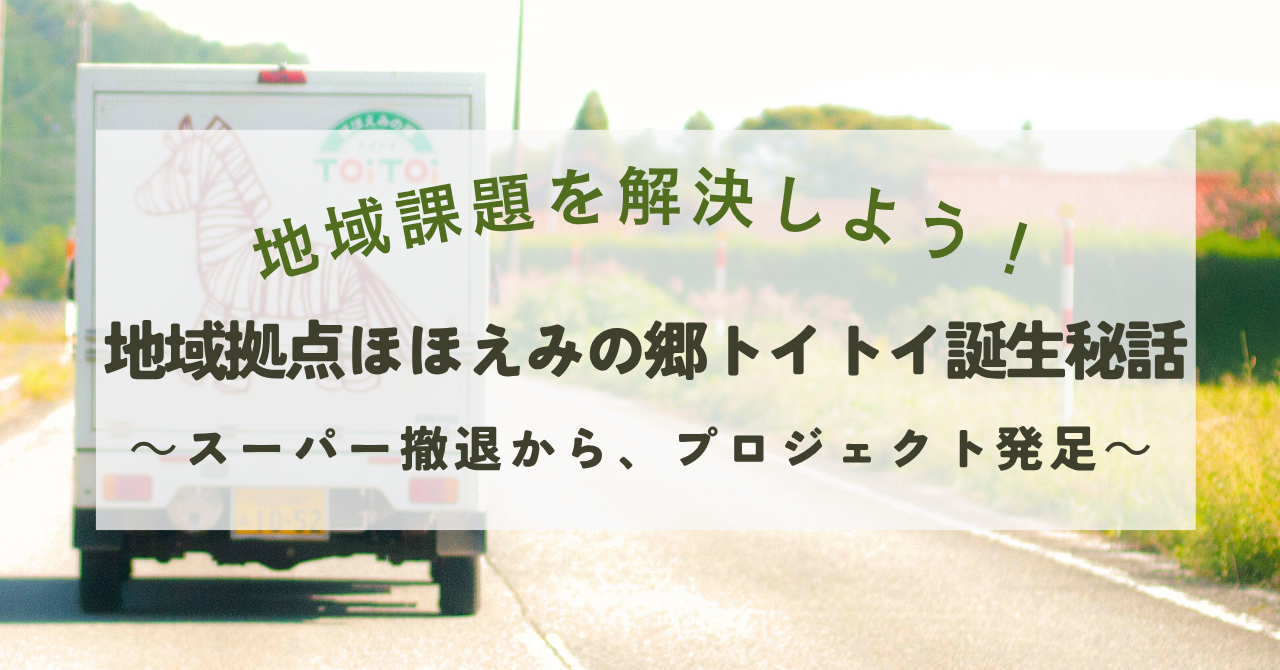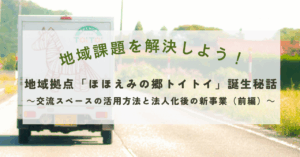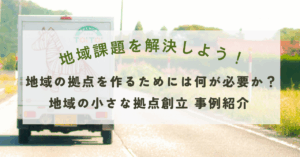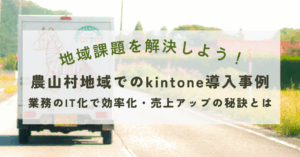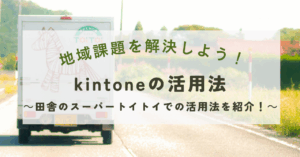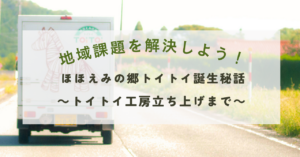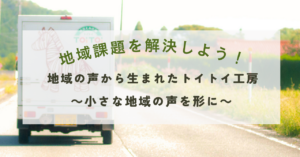高齢化率約60%、少子高齢化が著しく進む山口市阿東。阿東のような過疎化が進む農山村地域では、「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などの地域課題が深刻です。山口市阿東地福にある「小さな地域拠点」として地域の笑顔・安心・安全を見守り支える「ほほえみの郷トイトイ」。現在はその取り組みが総務省のふるさと大賞(優秀賞)に選ばれるほど、地域づくり・活性化の起点として活動されていますが、拠点立ち上げ時から現在に至るまでには様々な苦悩があったそうです。今回は、「ほほえみの郷トイトイ」事務局長である高田新一郎さんに、「小さな地域拠点」トイトイ設立の経緯についてお話を伺います。
スーパー撤退が突きつけた“暮らしの危機”――地域の小さな拠点「トイトイ」の原点
「スーパー撤退」がもたらした生活インフラ崩壊と住民の不安
-- 本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、阿東のような農山村地域では、都会のように気軽にコンビニやスーパーへ行くことができませんよね。コンビニに行くのも車で10分!なんて話は田舎あるでよく聞く話です。そんな中、地福地域にあった唯一のスーパーが撤退したことをきっかけに、ほほえみの郷トイトイが誕生したと伺いました。
高田 よろしくお願いいたします。当時、地福地域にはAコープというスーパーがありました。地域の方々にとっては「お店がある」ことが当たり前で生活の一部でした。そのAコープが撤退したことで、「買い物ができない」「生活の見通しが立たない」という不安が一気に地域住民の間で広がりました。特に高齢者の方にとっては、移動手段がない中で日常の買い物ができないというのは大きな問題でしたね。
--生活に直結する課題ですね。しかもそのタイミングが「平成の大合併」と重なったと聞きました。
高田 そうなんです。阿東町が山口市に編入された「平成の大合併※」が平成17年にありました。当時、行政体制の変化に加え、スーパー撤退という暮らしの基盤の崩壊が同時に起きたんですね。地域の将来に不安を抱く声も多く、「誰がこの地域の暮らしを守るのか」という問いが突きつけられた瞬間でした。
※「平成の大合併」とは、平成12年前半を中心に全国で進められた市町村の統合政策のこと。国の方針により、小規模自治体の行政効率化や財政健全化を目的に多くの町村が合併したが、一方で、旧町村の地域性や住民自治の弱体化、行政サービスの遠隔化など、地域にとって新たな課題も生まれた。阿東町も2005年に山口市へ編入合併し、行政体制や住民意識に大きな変化が生じた。
行政職員として感じた限界――地域を“支える側”から“動かす側”へ
合併後の行政現場に広がった“地域との距離感”
-- 高田さんは当時、市役所職員として地域に関わっておられたそうですね。
高田 はい。阿東総合支所で勤務していましたが、合併後は阿東について知らない(地域との関わりがそれまで一切ない)職員が増え、地域への熱量が違うこともあって、行政と地域との距離が広がっていくのを感じました。「地域づくり」や「地域課題解決」に積極的に取り組む職員は減り、阿東の現状を肌で感じられる人が少なくなってしまったんです。
--そうした中で、退職という決断をされたんですね。
高田 はい。上司からは「もう3年でいいからいてくれないか」と言われていましたが、40歳という節目を迎えたときに、「自分が地域にどう関わるか」を考え直しました。退職は「阿東のために」という使命感からではなく、自分の人生を地域に重ねるための選択でした。
地域づくり協議会の誕生と停滞――「誰も手を挙げない」現実
地域課題を共有し、「地域づくり協議会」での議論が始まる
--スーパー撤退を受けて、地域ではどのような動きがありましたか?
高田 地福地域では、老人クラブ、JA女性部、地福婦人会などの地域のコアメンバーが集まり、「地福地域づくり協議会」が立ち上がりました。最初の議論は「スーパーがなくなったから、次のスーパーをやってくれる人または団体を探そう」というものでした。私はまだその有志の中には参加していなかったのですが、人づてに話は聞いていた感じですね。
住民主体の議論が始まるも、企業誘致では限界が見えた
--そうなんですね。人材発見や企業の誘致はうまくいったのでしょうか?
高田 コープやまぐちに相談を持ちかけ、参入の話もありました。しかし、JAの跡地ということで競合関係がネックとなり、最終的には実現しませんでしたね。ゆめタウンなどスーパー事業を展開する企業へ相談をしに行ったこともありますが、「地福地域でのスーパー経営は難しい」という厳しい意見もありました。
そうして「スーパーがなくなった」ことを「スーパーをつくる」ことで解決しようとしていましたが、それは困難ではないかという結論に至りました。企業誘致という“外部依存”の解決策では、持続可能な地域づくりにはつながらないという現実にぶち当たることになりました。
--外部がだめなら、と地域で運営する案も出たそうですね。
高田 はい、地域で運営していく案もでていました。しかし、実際問題「自分がやる」と名乗り出る人はなかなかいませんでした。事業として責任を持つことへの不安、資金面の課題、経営のノウハウ不足…どれも現実的な壁がそこにあったからだと思います。議論は月2回ほど行われていましたが、1年近く経っても結論は出ず、議会は事実上の“頓挫”状態でしたね。
「スーパーをつくる」ではなく「地域をつくる」発想への転換
--まさに地域課題解決が行き詰まる典型的なパターンといえますが、そこからどう打開されたのでしょう?
高田 その時の協議会の会長・原田さんが「このままでは地域が動かない」と危機感を持ち、新たに私や長安正己さん(現トイトイ会長)をはじめ、外部のキーパーソン5名を集めて再スタートを切りました。
補助金など公的なお金を得るために「地域スーパー開業」のために行政を動かすことは難しいと考え、発想を転換して「地域のコミュニティの拠点」設立を目的として、スーパー機能はあくまでも付随するかたちで計画を立てました。
こうして「地域のコミュニティの拠点」設立という、地域課題解決のための従来の発想を大きく転換したんです。「スーパーをつくる」ことを目的にするのではなく、「地域の小さな拠点」をつくる。スーパー機能はその中の“ひとつの要素”にするという考え方ですね。
地域づくりのモデルとして発想の転換:「地域の小さな拠点」
「地域の小さな拠点」という新しい地域づくりのモデル
--地域コンサルの視点から見ても、その発想の転換は大きかったのではないでしょうか。
高田 そうですね。地域課題は「モノを補う」だけでは解決できません。そもそも人口減少や少子高齢化社会で担い手不足が都市部より深刻で、維持していくのがやっとという組織の方が多いでしょう。必要なのは、地域の人が集まり、情報が行き交い、支え合える“場”をつくること。つまり、「コミュニティ機能」を再構築することが、長期的な地域づくりの鍵になるんです。私たちは「買い物難民をなくす」ことを超えて、「地域に安心を生む場所」を目指しました。
--それが「ほほえみの郷トイトイ」という“地域の小さな拠点”の誕生につながったんですね。
高田 はい。最初の一歩は小さかったですし、方向転換をするまでに時間を時間を要しましたね。でも、この発想の転換がなければ、地域の未来も動き出さなかったでしょう。
約1年の停滞を超えて、地域が再び動き出す
--議論が始まってから、動き出すまでに約1年。その間も少子高齢化は止まらないという現実を考えると、きっと長い時間だったと思います。
高田 そうですね。課題を共有するだけでなく、解決のために“自分ごと”として動ける人を増やすのには時間がかかります。紆余曲折はありましたが、目の前に課題が立ちはだかってみて改めて地域の将来について考えるきっかけになりましたし、こうしてトイトイの基盤が生まれたとも言えるのではないかと思います。
--まさに、地域づくりの実践例といえますね。地域の「課題の本質」を見極め、持続可能な仕組みを生み出すプロセスそのものだと思います。
高田 そう言っていただけると嬉しいです。地域課題解決の出発点は、住民が「なぜ地域に必要なのか」を納得できること。そして、誰かが将来の一歩へ動き出す勇気を持つこと。それが“地域の変化”の種になるのだと実感しています。
地域の小さな拠点「トイトイ」誕生への道――資金集めの舞台裏へ
今回は、スーパー撤退から地域の拠点づくりへの発想の転換までを伺いました。
地域課題の本質を見極め、「スーパーをつくる」から「地域を支える場をつくる」へと転換した地福地域の挑戦は、まさに地域再生の原点といえます。
次回は、小さな拠点「ほほえみの郷トイトイ」誕生までのプロセスを掘り下げます。次回は、実際の立ち上げプロセスや運営の工夫、資金集め、地域への影響について詳しくお聞きします。立ち上げメンバーがどのように資金を集め、行政や住民とどう連携していったのか――そして、その後トイトイが地域の暮らしと意識をどう変えていったのかを詳しく伺います!
合わせて読みたい:ほほえみの郷トイトイ誕生秘話シリーズ
「ほほえみの郷トイトイ」は、スーパー撤退という地域の危機をきっかけに立ち上がった、住民主体の“地域拠点づくり”の事業です。その歩みを追う「ほほえみの郷トイトイ誕生秘話」シリーズでは、構想段階から法人化、そして地域に根づくまでの過程を詳しく紹介しています。
地域の小さな拠点誕生のために、プロジェクト発足と地域からどのように賛同してもらい資金集めをしたかを紹介しています。
地域拠点「ほほえみの郷トイトイ」誕生秘話 ~プロジェクト発足から資金集め~
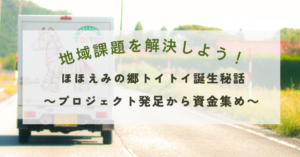
地域づくり事例の一つといえる、阿東地域での地域拠点「ほほえみの郷トイトイ」誕生。その資金集めから地域拠点誕生までを詳しく説明しています。
地域拠点「ほほえみの郷トイトイ」誕生秘話 ~資金集めからトイトイ誕生~
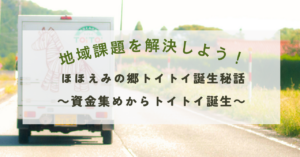
地域拠点として行ってきた事業展開について説明しています。また、法人化後にどのように地域の声に寄り添い、地域に欠かせない拠点となったのかについて解説しています。
地域拠点「ほほえみの郷トイトイ」誕生秘話 ~交流スペース活用と法人化後の新事業~